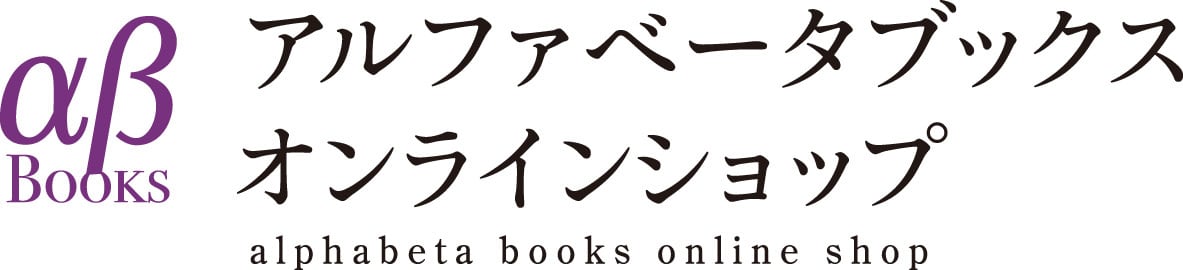-

増補新版 中山晋平伝 近代日本流行歌の父
¥2,970
《カチューシャの唄》《船頭小唄》《東京行進曲》《東京音頭》など、数々の名曲を生み出した日本歌謡曲のパイオニア・中山晋平。 近代日本音楽史、レコード産業史をバックグラウンドに、その魅力あふれる音楽個性と業績を辿る!! 優れた歌は、平和な時代にあってこそ生まれる。それは、不健康=センチメンタリズムから逆転できるバイタリティーとなる歌なのである。そのような優れた歌は、個人の自由が尊重される民主主義のなかで、きっと抒情と雄大なロマンチシズムに溢れた国民皆唱となるであろう。そのような意味においても、日本人の心情を表現する上で日本民謡のエネルギーに着目し、俗謡に宿るセンチメンタリズムを西洋音楽の技法で素朴・甘美に表現した中山晋平のメロディーに、今一度目を向けるべきではなかろうか。(本文「エピローグ」より) ※2007年に刊行された『近代日本流行歌の父 中山晋平伝』(郷土出版社)を加筆・修正した増補新版。「中山晋平―近代流行歌の時代」「中山晋平の民衆歌謡と宮沢賢治」を新たに増補。 中山晋平の生涯を描いた映画『シンペイ~歌こそすべて』が、1月10日より東京・TOHO シネマズ 日比谷ほかで公開‼ 歌舞伎俳優・中村橋之助が映画初出演にして初主演‼ 《目次》 1. 中山晋平の原郷 北信濃の風土と中山家 唱歌と笛 不遇な丁稚奉公 西洋音楽と文学への目覚め 代用教員時代 2. 苦闘の書生時代 島村家の書生 東京音楽学校 中山晋平の「新詩論」 音楽学校卒業 演歌から艶歌へ 3. レコード産業の夜明け エジソン―蓄音器・レコードの発明 エジソンに挑んだ男 米国ビクターの成立 日本のレコード・蓄音器の黎明 日本蓄音器商会の成立 4. 大正ロマンと近代流行歌の夜明け 女優・松井須磨子 「カチューシャの唄」 ゴンドラの唄 童謡運動 枯れすすき 5. 大正から昭和新時代へ 佐藤千夜子との出会い 歌を求めて―地方への旅 太平洋からの波 昭和流行歌前夜 晋平節―ラジオに登場 日本ビクターの成立 「出船の港」―藤原義江 「波浮の港」 6. 昭和流行歌と中山晋平 西條八十 日本ビクターの独走 東京行進曲 流行歌論争の周辺 エロ歌謡―愛して頂戴 エロ・グロ・ナンセンスの時代 カフェー歌謡 佐藤千夜子の洋行 異国の空に響く晋平節 古賀メロディーの登場 7. 大御所・中山晋平の面目 「銀座の柳」 新鋭・佐々木俊一 「燃える御神火」―藤山一郎ビクター入社 「東京音頭」の熱狂 さくら音頭合戦の勝利 佐藤千夜子の帰国 中山晋平―作曲生活二〇年記念音楽会 日本調歌謡と都市文化への讃歌 日本流行歌の系脈の複雑化 戦雲の日々 太平洋戦争 8. 中山晋平の戦後―新たな時代を生きて 虚脱と敗戦の混乱 歌謡曲の復活 戦後の復興 巨星落つ―人生の終焉 エピローグ 【増補・捨遺】 中山晋平―近代流行歌の時代 中山晋平の民衆歌謡と宮沢賢治 あとがき 《著者略歴》 菊池 清麿(キクチ キヨマロ) 音楽評論・歴史家。1960年、岩手県宮古市出身。明治大学政経学部卒、同大学院修了。明治大学マンドリン倶楽部では音楽を、橋川文三ゼミで思想史を研鑽。藤山一郎、古賀政男、中山晋平などの日本近代の大衆音楽関係者の評伝・伝記を執筆。 主な著書に、『永遠の歌姫佐藤千夜子』(東北出版企画)、『ツルレコード 昭和流行歌物語』(人間社)、『明治国家と柳田国男』(弦書房)、『日本流行歌変遷史』『私の青空 二村定一』『宮澤賢治 浅草オペラ・ジャズ・レヴューの時代』(以上、論創社)、『天才野球人 田部武雄』『評伝 古賀政男』『【新版】評伝 古関裕而』『日本プロ野球歌謡史』『【増補新版】評伝 服部良一』(以上、彩流社)、『昭和演歌の歴史』『昭和軍歌・軍国歌謡の歴史』(以上、アルファベータブックス)他多数。
-

太ったレディが歌うとき オペラの歴史はこう教わるもの
¥2,750
原書は初版から10年で6万部超のベストセラー! 世界中のオペラファンを楽しませてきたバーバーのユーモアオペラ史、待望の初邦訳。 オペラは難しくも堅苦しくもない! 400年にわたるオペラの歴史を、退屈な枝葉部分はスパっと切って、ユーモアたっぷりにお届けします。 イタリアのカストラートたちの運命、ヘンデルとソプラノ歌手との大喧嘩、プッチーニのニコチン中毒……音楽家たちの興味深いエピソードを織り混ぜながら、オペラ史のツボもしっかりと押さえます。面白くてためになるバーバー流の音楽史の世界へようこそ! この本を読めば、きっとあなたもオペラに行きたくなる! この本は実に聡明で素晴らしい読み物です。そして学校で音楽を学ぶ子供たちがこんな風に教わると良いのにと思うのです。――モーリーン・フォレスター(カナダ出身・往年の名アルト歌手) 《目次》 序文 モーリーン・フォレスター/アンナ・ラッセル 1 流行の始まり モンテヴェルディと音楽愛好家のグループ 2 一段上 カストラートは理性の玉を失う 3 真面目なおどけ オペラ・セリアとオペラ・ブッファ 4 フランス育ち リュリ、ラモー、グルック/ビゼー 5 イギリス海峡 ヘンデル 6 チュートン人のチューンスミス ハイドン/モーツァルト/ベートーヴェン 7 ロシア人の参入 グリンカ、五人組、そしてチャイコフスキー 8 隠された示導動機 ヴァーグナー 9 イタリアのソーセージ製造機 ヴィヴァルディ/ロッシーニ/ベッリーニ/ドニゼッティ/ヴェルディ/プッチーニ 10 エピローグ ――二〇世紀の残り物 《著者略歴》 デイヴィッド・バーバー(David W. Barber) デイヴィッド・バーバーはカナダのオタワ出身のジャーナリストで音楽家でもあり、彼には十数冊の著書がある。音楽書では本書のほか『Accidentals on purpose:Musician’s Dictionary』、『Bach,Beethoven and the Boys』、『Getting a Handel on Messiah』など。他に文学書『Quotable Sherlock』やバレエ、短編小説集、殺人ミステリーなどの著書もある。 彼はこれまでキングストン・ウィグ・スタンダード紙のライター、編集者、エンタテインメント編集者を務めた後、トロント・グローブ・アンド・メール紙のブロードキャスト・ウィーク誌の編集者、ポストメディア紙のアート&ライフ担当副編集長を経て、現在はフリーランスのライター、編集者をする傍ら音楽家、作曲家としても活動している。作曲家としては、交響曲が二曲、デイヴ・ブルーベックの音楽に基づくジャズ・ミサ曲、レクイエム、合唱曲や室内楽作品、種々の声楽ジャズ曲および編曲作品がある。彼はトロント室内合唱団の他にさまざまな合唱団で歌うこともある。これまで多彩な経験をしてきた中でも特に興味深いのは、短期間であったが、ローマ法王ヨハネ・パウロ二世のローディー、モナコのレーニエ公の広報担当、そしてアヴリル・ラヴィーンのバックアップ・シンガーを務めたことである。 彼の上記以外の著書については、本書の出版元である Indent Publishing. com をご参照いただきたい。また彼のブログは David W Barber. com である。なお彼の音楽についてはSheet Music Direct. com および Sheet Music Plus. com で検索することができる。 《訳者略歴》 石坂 廬(イシザカ イオリ) 1946年関東州大連市(現中国東北部)生まれ。東京都立新宿高校を経て早稲田大学卒。日本火災海上保険(現・損害保険ジャパン)に32年間勤務の後、笹川平和財団等に勤務。小学校よりコーラスを始め、高校文化祭で学生オペラ「真間の手古奈」に出演、早稲田大学グリークラブで男声合唱を行う。発声を田島好一、金谷良三の両氏に、イタリア歌曲等を渡部成哉氏に学ぶ。これまで海外との文化交流ではイスラエル、西ドイツ、オーストリア、ラトヴィア、英国、中国、台湾を訪問し、合唱祭や演奏会に男声唱団員として参加。現在稲門グリークラブ、日本ラトヴィア音楽協会の各会員。訳書にノア・ベンアルツィ著『悲しみと希望――ラビン首相の孫が語る祖父、国、平和』(ミルトス)、サミュエル・チョツィノフ著『トスカニーニ 身近で見たマエストロ』、コスティ・ヴェハーネン著『マリアン・アンダースン』(ともにアルファベータブックス)がある。 《イラストレーター略歴》 デイヴ・ドナルド(Dave Donald) デイヴ・ドナルドは描かなかった時期を思い出せないぐらい子供の頃よりありとあらゆるものに自分の絵を描き連ねてきたので、今それが生業になっていることは少しも驚くことではない。彼は現在、フリーランスとして出版デザインに携わりながら、より奥深い芸術作品を追求することとのバランスを取りつつ仕事を続けている。この本は多数あるデイヴィッド・バーバーとのコラボレーションによるイラストの一冊である。
-

バロック音楽の基礎知識 盛期および後期バロックの器楽曲について
¥1,980
難解なバロック音楽の理論を分かりやすく学べる入門書の決定版! フランクフルト音楽・舞台芸術大学のプログラム(歴史的演奏実践)の一環として出版された、バロック音楽の入門書。対話形式で書かれており、要点が簡潔にまとめられているため、難解なバロック音楽を分かりやすく学ぶことができる。巻末には付録として用語集とミニテストを収録。学生、音楽教師、音楽家から愛好家まで、バロック音楽の知識を深めたい方に最適な1冊。 《目次》 まえがき 時代について 音楽の普及 調律とピッチ 協奏曲 ソナタ 組曲と舞曲の種類 様式 テンポと拍 装飾 (付録) 用語集 ミニテスト 《著者略歴》 カール・カイザー (Karl Kaiser) フランクフルト音楽・舞台芸術大学およびフライブルク音楽大学のフラウト・トラヴェルソと歴史的演奏実践の名誉教授を務める。 ケルン室内合奏団、ラ・スタジオーネ・フランクフルトおよびアルディンゲロ・アンサンブルのフルート奏者。ほぼ30年間にわたり、フライブルク・バロックオーケストラの首席フルート奏者を務め、世界各地の舞台で演奏を行う。ケルン室内合奏団、アルディンゲロ・アンサンブルのフルート奏者として、バロックからロマン派に至るまでのピリオド楽器を用いた室内楽曲を多数CDに録音。またフライブルク・バロックオーケストラ、ケルン室内合奏団のソリストとして、ヴィヴァルディ、テレマン、バッハおよびその息子たち、アーベル、ホルツバウアーなどの作曲家によるフルート協奏曲を演奏し、録音も多数残している。 著者としては18世紀および19世紀の歴史的実践および方法論に関するテーマを研究対象としている。 《訳者略歴》 白井 美穂(シライ ミホ) 名古屋芸術大学音楽部器楽学科を首席で卒業。デュッセルドルフ・ロベルト・シューマン音楽大学でベーム式フルートのディプロマを最優秀で取得し、室内学科を審査員満場一致の最優秀賞で卒業。エッセン・フォルクヴァンク芸術大学およびフランクフルト音楽・舞台芸術大学の古楽科マスター課程を修了。2017年から2019年までカール・カイザー氏にフラウト・トラヴェルソと多鍵式フルートを師事。ドイツ語では「ゲーテ・インスティテュート」のC2(最高レベル、母国語レベル)を所持。17年間のドイツ滞在を経て、日本に拠点を移し、演奏活動とともに翻訳、通訳活動にも従事している。 2023年よりフルート専門誌「THE FLUTE」にフラウト・トラヴェルソとバロック音楽に関する連載を寄稿。
-

吉田進のクロスオーバー音楽塾
¥2,750
西洋と東洋を超えた独自の視点で音楽を語る作曲家・吉田進の人気講座を書籍化! クラシック音楽のほかに、シャンソン、ロック、ジャズ、演歌などのさまざまな音楽を、バレエ、映画、美術、文学、歴史など、さらにさまざまなジャンルと結びつけ(クロスオーバー)、縦横無尽に語ります。 人間の営みには国境を越えていつも音楽があった。音楽についての視野が広がる一冊。 ≪目次≫ はじめに 1 ジョルジュ・サンドから見たショパン 2 《椿姫》に乾杯! 3 シャンソンの名歌《桜んぼの実る頃》秘話 4 世界の国歌を考える 5 わが師メシアン 6 フリーメイソンと音楽 7 演歌へのラブレター 8 僕のパラドックス音楽人生 僕はなぜ講演をするのか ~ あとがきに代えて 《著者略歴》 吉田 進(ヨシダ ススム) 作曲家。1947年、東京に生まれる。1970年、慶應義塾大学経済学部卒業後、池内友次郎、大月玄之両氏に師事。1972年、渡仏。パリ国立高等音楽院対位法科(一等賞)、和声法科(二等賞)修了後、作曲科でオリヴィエ・メシアン氏に師事(一等賞)。パリ在住。 代表作に《演歌》シリーズ、《空蟬》、《神巫》、《五つの俳諧》、能オペラ《隅田川》、ヴァイオリン協奏曲《四季》、歌劇《地獄変》などが、著書に『ラ・マルセイエーズ物語』(中公新書)、『パリからの演歌熱愛書簡』(TBSブリタニカ)、『フリーメイソンと大音楽家たち』(国書刊行会)、『パリの空の下《演歌》は流れる』(アルファベータブックス)がある。
-

検証・80年代日本のロック
¥2,750
1980年代―それは日本のロックが独り立ちした時代だった‼ 60年代にビートルズやローリング・ストーンズが世に知らしめて、70年代にハード・ロックやプログレッシヴ・ロックのバンドたちが発展させたロックを吸収し、それを自分たちなりの新たな形で提示し、日本のロックもようやく「日本語の」、また「日本人の」なんて但し書きをつけずに、ただ「ロック」と語られるようになった1980年代の日本のロック・アーティストたちの姿を、音楽雑誌『ミュージック・ステディ』(※)編集長として、また数々の音楽雑誌の記事執筆やケーブル・テレビの音楽番組の制作などを手がけた音楽ジャーナリストとして深くかかわりを持った著者が検証、考察。また、レーベルやイヴェント、ライヴハウス、音楽メディア等々についても、あまり知られていない裏話的なことも盛り込みながら記す!! ※『ミュージック・ステディ』 日本のロックをメインに取り上げた音楽雑誌。1980年代初頭に、当初は季刊としてスタート、のちに隔月刊になり、84年半ばに月刊化する。著者・小島智は85年初頭から、その2代目の編集長を休刊まで務める。RCサクセションやハウンド・ドッグ、また佐野元春や浜田省吾、サザンオールスターズといったロックのビッグ・ネームとともに、ムーンライダーズなどの個性派やスターリンなどのパンク系も同列に取り上げた誌面作りが話題を集めた。モッズやシーナ&ザ・ロケッツなどのビート系、尾崎豊や吉川晃司、渡辺美里や中村あゆみら新世代にも早い時期から注目していた。 ≪目次≫ 1. 独り立ちした日本のロックの象徴/ RCサクセション 2. 思い出深い3バンド/ハウンド・ドッグ、ARB、ザ・モッズ 3. 日本のロックに色を添えた/ストリート・スライダーズ、BOØWY 4. 元気だったビート系とパンク系/ルースターズ、ロッカーズ、シーナ&ザ・ロケッツ、アナーキー、スターリンetc. 5. 圧倒的に人気が高かった二人のシンガー・ソングライター/佐野元春、浜田省吾 6. 80年代に登場した新型ポップ/大沢誉志幸、大江千里etc. 7. 女性によるロックの道筋をつけた/山下久美子・白井貴子 8. 祭り上げられたカリスマ像との葛藤/尾崎豊 9. 尾崎に続いたティーンエイジ・ガール二人/渡辺美里、中村あゆみ 10. 黄色人種独特のチャンキー・ミュージックを世界に発信/ YMO 11. 独自の活動を続けた都会派実力バンド/ PINKほかキリング・タイム、リアル・フィッシュetc. 12. イカ天から登場した本格派/ザ・ブランキー・ジェット・シティ 13. 80年代後半から脚光を浴び始めたヴィジュアル系/ BUCK-TICK、X(X JAPAN)etc. 14. ロックと歌謡曲のはざまで/チェッカーズと吉川晃司etc. 15. バンド・ブームの立役者たち/ザ・ブルーハーツ、アンジー、ジュン・スカイ・ウォーカーズetc. 16. 粘り強く活動を続けたキャリア組・1 /竹田和夫、チャー、カルメン・マキetc. 17. 粘り強く活動を続けたキャリア組・2 /上田正樹とサウス・トゥ・サウス、ウエスト・ロード・ブルース・バンド、ソー・バッド・レビューetc. 出身の、関西ブラック・ミュージック系アーティスト 18. 80年代に支持を得た、ほかのアーティスト何組か 19. 80年代はアンダーグラウンド・シーンからも発信があった 20. 活況を呈したライヴハウス・シーン 21. やはり80年代から盛り上り始めたコンサートや大規模イヴェント 22. 注目を集めた80年代の音楽雑誌 《著者略歴》 小島 智(コジマ サトシ) 東京都出身。明治大学在学中よりミニコミ編集やイヴェント制作にかかわるようになり、卒業後、コンサート制作会社、音楽プロダクションでアーティスト・マネージメントなども体験。80年代半ばに月刊『ミュージック・ステディ』の編集部に参加、のち同誌編集長。80年代後半からはフリーで音楽誌を中心に一般誌、新聞などに音楽評論、アーティスト・インタビュー記事などを執筆。著書に『ロック& ポップスの英語歌詞を読む』(ベレ出版)、『「人間・ビートルズ」入門』(宝島社)、『ビートルズで英会話』(ベストセラーズ)、『アヴァン・ミュージック・イン・ジャパン』『ビートルズの語感 曲づくりにも共通する遊びの発想』(以上、DU BOOKS)など。
-

トスカニーニ 良心の音楽家(下) 決して不在でなかったマエストロ
¥5,940
二十世紀の最も活動的で影響力の大きい音楽家であり並外れた人間であったトスカニーニの、非凡な生涯とキャリアを描いた全く新しい伝記! 上下巻で1000 頁を超える大作!! 他の人々が作曲した作品を理解し公演するのが仕事である解釈音楽家として自らの良心に従っただけでなく、他の音楽家との関係、また人間の自由と公正を強く信奉する人間としても自らの良心に従った、良心の音楽家、巨匠トスカニーニの生涯を描く !! この素晴らしい伝記が完訳されたことに感謝! 緻密にして克明、目の前に立ち現れる稀代の大指揮者トスカニーニに、感服、敬服、平伏です!――檀ふみ トスカニー二に関わる著者畢生の伝記。ヴェルディを始め、オぺラ演奏史として価値ある著作――鈴木幸一IIJ 会長、東京・春・音楽祭実行委員長推薦‼ エコノミスト誌及びカーカス・レビューズの年間最優秀書籍‼ 並外れている(ティム・ペイジ、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス誌) 説得力があり感動させずにはおかない(ロバート・ゴットリーブ、ニューヨーク・タイムズ・ブック・レビュー誌) 疑いなく、これまで出版された最も魅力的で、最も見事に書かれ、そして、確かに最も包括的なトスカニーニの伝記(ロブ・カウワン、グラモフォン誌) 記念碑的(アレックス・ロス、ザ・ニューヨーカー誌) 私は音楽と倫理的問題に関心のある人すべてに『トスカニーニ 良心の音楽家』を推薦したい(ダニエル・バレンボイム) 「大きな業績」として多くの人に歓迎されたハーヴィー・サックスの『トスカニーニ 良心の音楽家』は、見事に書かれ完璧に調査された書籍であり、この永遠に論争を呼ぶ人物についての将来の議論すべてが同書と取り組まなければならないだろう(サイモン・ウィリアムズ、ロサンゼルス・レビュー・オブ・ブックス誌) 並外れている(ティム・ペイジ、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス誌) 説得力があり感動させずにはおかない(ロバート・ゴットリーブ、ニューヨーク・タイムズ・ブック・レビュー誌) 疑いなく、これまで出版された最も魅力的で、最も見事に書かれ、そして、確かに最も包括的なトスカニーニの伝記(ロブ・カウワン、グラモフォン誌) 《目次》 【上巻】 第1章 不確定なそして確定したサウンド 第2章 あご髭の無いマエストロ 第3章 トリノ 第4章 スカラ座改革 第5章 ニューヨーク メトロポリタン 第6章 幕間 第7章 スカラ座再創造 【下巻】 第8章 ニューヨーク・フィルハーモニックと新しい地平 第9章 水晶のように明快かつ痛烈で 第10 章 国外追放と帰還 第11 章 フィナーレ コーダ 《著者略歴》 ハーヴィー・サックス(Harvey Sachs) 『Toscanini』、『Music in Fascist Italy』をはじめ11 冊の著書、共著がある。ニューヨーク市在住。フィラデルフィア市のカーティス音楽院の講師。 《訳者略歴》 神澤 俊介(かんざわ しゅんすけ) 1978 年東京大学法学部卒、1983 年シカゴ大学MBA。東京、NY での金融機関勤務を経て、2007 年(株)ライトフラッツ代表取締役、2012 年より東京大学校友会事務局長を兼職。
-

バイロイト祝祭の黄金時代 ライヴ録音でたどるワーグナー上演史《叢書・20 世紀の芸術と文学》
¥4,620
SOLD OUT
ドイツの巨匠ワーグナーが遺したオペラのみを上演するバイロイト祝祭。当代一の歌手と指揮者と、気鋭の演出家による公演は常に話題となり、世界で最もチケットが取りにくいとされる。バイロイト祝祭の戦後最初の1951年から1970年代半ばまでの「新バイロイト」の「黄金時代」を現存するすべての録音記録をもとに徹底検証。世界にも例のない、ワーグナー上演史。 【登場する主な指揮者・歌手】 フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュ、カラヤン、カイルベルト、クレメンス・クラウス、ヨッフム、クリュイタンス、サヴァリッシュ、マタチッチ、ラインスドルフ、ケンペ、マゼール、クリップス、ベーム、スウィートナー、ブーレーズ、カルロス・クライバー、ヴァルナイ、メードル、ニルソン、ヴィントガッセン、ホッター、ナイトリンガー、グラインドルほか 《目次》 前史 ―1904~27年 序章 全曲録音が始まる ―1928~1944年 第1章 再出発 ―1951年 第2章 常連歌手たちの集結 ―1952年 第3章 クレメンス・クラウス、ひと夏だけの輝き ―1953年 第4章 幻のマルケヴィッチの《タンホイザー》―1954年 第5章 クナッパーツブッシュvs カイルベルト ―1955年 第6章 新バイロイトの第2ラウンド ―1956年 第7章 新鋭サヴァリッシュの抜擢 ―1957年 第8章 「青の時代」ヴィーラント演出の《ローエングリン》―1958年 第9章 ヴィーラントの理想の「相棒」―1959年 第10章 ルドルフ・ケンぺの試練 ―1960年 第11章 ベジャールとのコラボレーション ―1961年 第12章 カール・ベーム68歳のバイロイト・デビュー ―1962年 第13章 転換期を迎えた新バイロイト ―1963/64年 第14章 ヴィーラント・ワーグナーの死 ―1965~67年 第15章 ヴォルフガング・ワーグナー単独体制の始動 ―1968~70年 第16章 嵐の前の静けさ ―1971~75年 《バイロイト祝祭》 バイロイト祝祭(バイロイト音楽祭)は、1876年にリヒャルト・ワーグナーが自作のオペラを上演するために設立した音楽祭。毎年夏に、ワーグナー作品のみが上演されている。ここに出演することは、歌手、指揮者にとって最大の名誉であり、あまたの名演が残された。戦後は毎年ラジオで生放送されているため、録音・録画の多さでも群を抜いている。 《著者略歴》 吉田 真(ヨシダ マコト) 1961年生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得。専攻はドイツ文学(ワーグナー研究)。現在、明治学院大学准教授、慶應義塾大学講師、日本大学芸術学部講師。 著書:『作曲家・人と作品 ワーグナー』(音楽之友社)。共著書:『スタンダード・オペラ鑑賞ブック ドイツ・オペラ 下』、『オペラ・キャラクター解読事典』、『栄光のオペラ歌手を聴く!』(以上、音楽之友社)、『ワーグナー事典』(東京書籍)、ほか。共訳書:ハンス=ヨアヒム・バウアー『ワーグナー王朝』(音楽之友社)、ほか。監訳書:ブリギッテ・ハーマン『ヒトラーとバイロイト音楽祭 上・下』(アルファベータ)。
-

トスカニーニ 良心の音楽家(上) 歌劇界での人生
¥5,940
二十世紀の最も活動的で影響力の大きい音楽家であり並外れた人間であったトスカニーニの、非凡な生涯とキャリアを描いた全く新しい伝記! 上下巻で1000 頁を超える大作!! 他の人々が作曲した作品を理解し公演するのが仕事である解釈音楽家として自らの良心に従っただけでなく、他の音楽家との関係、また人間の自由と公正を強く信奉する人間としても自らの良心に従った、良心の音楽家、巨匠トスカニーニの生涯を描く !! トスカニー二に関わる著者畢生の伝記。ヴェルディを始め、オぺラ演奏史として価値ある著作――鈴木幸一IIJ 会長、東京・春・音楽祭実行委員長推薦‼ エコノミスト誌及びカーカス・レビューズの年間最優秀書籍‼ 《目次》 【上巻】 第1章 不確定なそして確定したサウンド 第2章 あご髭の無いマエストロ 第3章 トリノ 第4章 スカラ座改革 第5章 ニューヨーク メトロポリタン 第6章 幕間 第7章 スカラ座再創造 【下巻】 第8章 ニューヨーク・フィルハーモニックと新しい地平 第9章 水晶のように明快かつ痛烈で 第10 章 国外追放と帰還 第11 章 フィナーレ コーダ ※「(下) 決して不在でなかったマエストロ」は6月刊行予定 《著者略歴》 ハーヴィー・サックス(Harvey Sachs) 『Toscanini』、『Music in Fascist Italy』をはじめ11 冊の著書、共著がある。ニューヨーク市在住。フィラデルフィア市のカーティス音楽院の講師。 《訳者略歴》 神澤 俊介(かんざわ しゅんすけ) 1978 年東京大学法学部卒、1983 年シカゴ大学MBA。東京、NY での金融機関勤務を経て、2007 年(株)ライトフラッツ代表取締役、2012 年より東京大学校友会事務局長を兼職。
-

溢奏(いっそう) ラフマニノフに聴く演奏の極意
¥2,970
ラフマニノフ国際ピアノコンクールの覇者が、正教をとおして見出したロシア・クラシック音楽の真髄。 好評を博した『ラフマニノフを弾け』の姉妹版、ついに刊行! その後、7年間にわたる思索の軌跡。多くの人を魅了してやまないラフマニノフの音楽は、正教を抜きにしては語れない。本書では、ラフマニノフをはじめとするロシアの偉大な音楽家、音楽学者たちの声に耳を傾け、その根底に流れる信仰の心を深く感じとり、音楽とは何か、音楽家の使命とは何かを追求していく。自筆論文3本、和訳論文4本を収録。巻末には、正教の聖人やロシアの詩人の深遠な言葉も掲載。 弾くことの意味を求めるあなたへ贈る、精神的な道しるべとなる一冊。 【編著者より】 ピアノを弾く。その向こうに、何があるのか。何を観て、何のために弾くのか。 この問いは「何のために生きるのか」という問いに直結する。目的が人生のすべてを変える以上、どういう目的を持つかが肝心だ。 キリスト教は、天国という目的を持てと教える。それは力づくで奪うもの(マタイ11:12)、つまり努力して得るものであり、しかも、わたしたちの内にある(ルカ17:21)、という。 ピアノは心で弾くものであって、頭や指で弾くものではない。心から音楽が溢れてくるにはどうしたらいいのか、その点を追求した成果が一冊の本になった。自分で書いた論文だけでなく、このテーマに関するロシア語の文献も和訳した。ラフマニノフ著「優れたピアノ演奏に典型的な10の特長」も入っている。「音楽――それは愛!」とラフマニノフは言う。そういう演奏を目指す方は、ぜひ一度手に取って読んでみていただきたい。 《目次》 第1章 音楽の創造力の探求(土田定克) 第2章 ラフマニノフの芥子種(土田定克) 第3章 ロシア音楽のロゴスへの道(ガリマ・ルキナ) 第4章 音楽と存在にみる天の闡明 (ヴャチェスラフ・メドゥシェフスキー) 第5章 優れたピアノ演奏に典型的な10 の特長 (セルゲイ・ラフマニノフ) 第6章 神父と信徒芸術家 (聖イグナティ・ブリャンチャニノフ) 第7章 永遠の愛を宣べ伝えるために(土田定克) 付録1 『修行訓話』抜粋集(シリアの聖イサアク) 付録2 ロシアの十字架(ニコライ・メリニコフ) 【編著者略歴】 土田 定克(ツチダ サダカツ) 1975年、東京生まれ。桐朋学園大学音楽学部ソリスト・ディプロマコースを経てモスクワ音楽院卒業、同大学院修了。小西由紀子、坂田晴美、兼松雅子、A.ムンドヤンツ、V.メルジャノフに師事。第3回ラフマニノフ国際コンクール第1位(2002年、モスクワ)。ロシア各地、ウクライナ、クロアチア、タイ、韓国等はじめ、国内(東京文化会館、東京オペラシティ、すみだトリフォニーホール、カザルスホール、練馬文化センター、横浜みなとみらいホール等)でも演奏会多数。名指揮者V.フェドセーエフ率いるモスクワ放送交響楽団や、M.タルブク率いるHRTクロアチア放送交響楽団、三ツ橋敬子指揮・東京フィルハーモニー交響楽団はじめザグレブ弦楽四重奏団など、オーケストラや室内楽との共演も多数。CD「ラフマニノフ 24のプレリュード」「ピアノ名曲集 乗り越えて」をリリース。2016年、自著『ラフマニノフを弾け』を上梓。同ロシア語版『Россия и Рахманинов глазами японского музыканта』もモスクワから出版。親善的な演奏活動に対し、ロシアのペルミ市長(2004年)や韓国の群山警察署長(2016年)、ウクライナの第2代大統領クチマ(2018年)より功労感謝状授与。尚絅学院大学教授。宮城学院女子大学音楽科非常勤講師。 ※本書の著者出演のイベントのお知らせ 12月15日(金)に「三田市総合文化センター郷の音ホール」にて開催される「ラフマニノフ生誕150周年記念コンサート」にて、『ラフマニノフを弾け』の著者で12月に新刊『 溢奏(いっそう) ラフマニノフに聴く演奏の極意』を刊行する土田定克氏(ピアノ)とナターリア・コズローヴァ(ソプラノ)の協演が開催されます。 新刊『 溢奏(いっそう) ラフマニノフに聴く演奏の極意』と既刊の『ラフマニノフを弾け!』も会場で販売いたします。 『ラフマニノフ生誕150周年記念コンサート 土田定克(ピアノ)+ナターリア・コズローヴァ(ソプラノ)」 https://sanda-bunka.jp/wp-content/uploads/1215_%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%B4%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%81%AE%E4%BC%9A.pdf 場所:三田市総合文化センター郷の音ホール・小ホール 日時:2023年12月15日(金) 時間;18:30 料金:2,500円(学生1,000円)(自由席) 問い合わせ先 郷の音ホールチケットセンター 〒669-1531 兵庫県三田市天神1-3-1 TEL:079-559-8101 スラヴ音楽の会 TEL:06-6763-0877 MAIL:[email protected]
-

ルービンシュタイン 全録音をCDで聴く
¥4,180
ルービンシュタインの生涯にわたってなされた全ての録音(1928~1976)を彼の人生においての出来事とともに論じ、CDで聴けるようにガイドする。 前回好評だった『ホロヴィッツ全録音をCD で聴く』に続く、シリーズ第2弾! 「己の演奏を後世に残す」という強い使命感を持って晩年まで録音に挑み続けたピアニストのアルトゥール・ルービンシュタイン(1887~1982)。彼の代名詞とも言えるショパンの演奏をはじめ、全ての録音データを網羅するとともに、彼の音楽人生も辿っていく。 【全録音ディスコグラフィー付】 《著者略歴》 藤田 恵司(ふじた けいじ) 1978年1月22日、20世紀を代表するピアニスト、ウラディミール・ホロヴィッツ(1903~1989)のアメリカ・デビュー50周年記念演奏会の2週間後に生まれる。中1のときにたまたま音楽の授業で聴いた往年の名ヴァイオリニスト、ミッシャ・エルマン(1891~1967)の弾く「ツィゴイネルワイゼン」[VANGUARD]がきっかけでクラシック音楽の魅力に目覚める。後に旭川出身の音楽評論家、故・佐藤泰一氏(1938~2009)との親交やコンサートで旭川をたびたび訪れたウィーンのピアノの巨匠、故・イェルク・デームス(1928~2019)に接し、ピアノ曲やピアニストにおける世界の奥深さを知る。2007年9月から2009年8月まで旭川市・大雪クリスタルホールの運営協議委員を務める。「クラシックジャーナル047 クラシックCD 最終形態としてのBOX」(アルファベータ2013年)中の「50のBOXに聴くピアニストの至芸」を執筆。著書に『ホロヴィッツ 全録音をCDで聴く』(アルファベータブックス 2019年)がある。
-

鍵盤に指を置くとき トゥレットは僕の個性
¥1,980
音楽を通じて、多くの人にこの難病への理解を広げたい 自分の意思にかかわらず、身体が動いたり声が出てしまったりする神経疾患「トゥレット症候群」。8歳で発症後、チック症状に悩まされ、生きていくうえで様々な困難にぶつかりながらも、ピアニストとして、人間として成長していったYUSK がその人生を綴る!! 症状が悪化し、ピアノさえ手につかない時もあったYUSK が、それでも人生を立て直し、元の軌道に戻れたのはピアノの存在のおかげだった。ピアノの鍵盤に指を置くと、その瞬間にチック症状が消えた……奇跡がおきた瞬間だった。 トゥレット症と闘う中原中也賞受賞詩人・須藤洋平氏推薦! 「僕らはなんだかんだで、ここまでやってきたんですもの。それはもう既に、奇跡だと思うのです。」(須藤洋平) ※トゥレット症候群とは 「チック」と呼ばれる突発的、急速で反復的、非律動的な運動や音声が自分の意志とは関係なく突然現れ、繰り返す症状が1 年以上みられる病気で小児期に発症する。チックは、運動チック(まばたき、首振り、肩すくめ、顔しかめ、自分を叩くなど)と、音声チック(咳払い、鼻すすり、叫ぶ、特定の言語を繰り返すなど)がある。 《著者略歴》 YUSK(ユウスケ) 佐賀県出身。6ヵ月で父親のロンドン赴任に伴いイギリスに渡る。5歳から鈴木メソッドでピアノを始める。7歳までロンドンで生活後、ジュネーブ、東京、ニューヨーク、再びロンドンへと父親の赴任地が変わるたびに転居を繰り返す。生活環境の急激な変化により8歳のときトゥレット症候群を発症。言葉による音声チックと、首振りやまばたきなどを繰り返す運動チックの二つがさまざまな形で現れる。薬の副作用に苦しむも、好きなピアノを弾いているときは症状が出なかった。ニューヨークのジュリアード音楽院、英国チーダム音楽学校(首席)卒業、同時にヘンリーウッド音楽賞を受賞。2000年、ドイツのベルリン芸術大学に最高点で入学。その後、6年間トゥレット症候群の為、演奏活動を休止。ベルリン芸術大学を退学後、ドイツのハノーファー音楽大学に入学、ベルント・ゲツケ、ミーキョン・キムの両氏に師事。2009年、ロンドンで復帰コンサート。2014年、同大学院修士課程修了。クリストファー・デューク・メモリアル・コンクール第2位、ヨーロッパ・ベートーヴェン・コンクール第2位、ダドリー国際ピアノ・コンクール・ファイナリスト。現在、英国王立音学院非常勤講師、及びロンドン交響楽団(London Symphony Orchestra)の専属ピアニスト。
-

フェレンツ・フリッチャイ 理想の音楽を追い続けて
¥3,190
「フルトヴェングラーとトスカニーニの間に位置する」と評されたその特異な芸風はどのように形成されていったのか。 ドイツを中心にヨーロッパやアメリカで活躍したハンガリー出身の指揮者、フェレンツ・フリッチャイ。戦争、音楽界での対立、そして病……多くの困難に直面しながらも、自らが理想とする音楽を追い続け、その中から特異な芸風を創り上げていった名匠の生涯を辿る。 *フェレンツ・フリッチャイ 1914年、ブダペスト生まれ。フランツ・リスト音楽院卒業。指揮者。セゲド・フィルハーモニー、ブダペスト国立歌劇場、ハンガリー国立交響楽団の音楽監督を歴任。戦後はベルリンのRIAS交響楽団首席指揮者、バイエルン州立歌劇場音楽監督等を歴任、欧米各地に客演。1958年秋ごろより白血病の症状が現れ、1963年、スイスのバーゼルにて48歳で亡くなる。 【目次】 第1章 幼少期から大学卒業まで 第2章 セゲドで指揮者として活動開始、実力を蓄える 第3章 ウィーン客演とザルツブルク音楽祭デビュー 第4章 ベルリン・デビューとRIAS交響楽団首席指揮者就任(第一期ベルリン時代その一) 第5章 RIAS交響楽団を一流オーケストラに(第一期ベルリン時代その二) 第6章 ヒューストン、ミュンヘンでの活動 第7章 晩年(第二期ベルリン時代) 付 章 特に忘れ難い演奏 資 料 ディスコグラフィ *ほか、コラムも充実 【著者略歴】 大脇 利雄(オオワキ・トシオ) 1958年6月、群馬県安中市生まれ。1982年、筑波大学第一学群自然学類(数学主専攻)卒業。同年日本国有鉄道入社、1987年、国鉄分割・民営化に伴い東日本旅客鉄道株式会社に入社、安全対策部門で16年勤めた後、籠原運輸区副区長、安中榛名駅長を歴任。2011年、JR東日本メカトロニクス株式会社に出向、2019年6月、定年で退職。吾妻線CTC(列車集中制御装置)の信号を操作する時期をアラームで知らせるプログラムをBASICで作成。高鉄運転史『轣轆114』編集委員、原稿の一部を担当、また数枚の写真を提供。書籍『伝説の指揮者フェレンツ・フリッチャイ』(アルファベータブックス)では資料を提供。2000年11月にウェブサイト「My Favorite Fricsay」を開設。
-

時代を超えて受け継がれるもの ピアニストが語る!《現代の世界的ピアニストたちとの対話 第五巻》
¥3,960
大好評の人気シリーズ第5弾! 偉大な巨匠たちの言葉、ピアノ教育の変遷、個性豊かな若手ピアニストたち、ピアニズムのグローバル化、室内楽の魅力……世界的ピアニストたちが長時間インタビューに応じ、芸術、文化、政治、社会、家庭、人生について語る! <本書に登場するピアニスト> イェルク・デームス/パウル・バドゥラ= スコダ/メナヘム・プレスラー/ホアキン・アチュカロ/ゲイリー・グラフマン/ネルソン・フレイレ/ユジャ・ワン/アレクサンダー・ガヴリリュク/ラファウ・ブレハッチ/ピョートル・アンデルジェフスキ/アレクサンドル・タロー/ナターリア・トゥルーリ/イェフィム・ブロンフマン/ドミトリー・アレクセーエフ 【著者略歴】 焦 元溥(チャオ・ユアンプー, Yuan-Pu Chiao) 1978年、台北に生まれる。国立台湾大学政治学部国際関係学科を卒業後、アメリカに渡り、2005年、フレッチャー法律外交大学院(The Fletcher School, Tufts University)修士課程(Master of Arts in Law and Diplomacy)終了。2008年から2009年、大英図書館の特別研究員(Edison Fellow)としてキングス・カレッジ(Kingʼs College, London)にて音楽学を専攻し、博士課程修了。著述家、研究者、音楽ジャーナリスト、講座や放送番組のプレゼンターとして活躍している。「20×10 ショパン・フェスティバル」「Debussy Touch ドビュッシー・ピアノ・フェスティバル」などの音楽祭を企画。『楽之本事̶古典音楽聆聽入門』など10作以上の著書があり、2019年に出版された本書の原著『游藝黒白̶世界鋼琴家訪問録』の増訂新版には、108人のピアニストのインタビユーが収録されている。 【訳者略歴】 森岡 葉(モリオカ・ヨウ) 慶應義塾大学法学部政治学科卒業。1974年~ 76年、北京語言学院、北京大学に留学。音楽ジャーナリスト。著書に『望郷のマズルカ̶激動の中国現代史を生きたピアニストフー・ツォン』(ハンナ)、訳書に『ピアニストが語る! 現代の世界的ピアニストたちとの対話』シリーズ(アルファベータブックス)。
-

セザール・フランク
¥2,750
セザール・フランクをよりよく知り、 より多く愛するための真の福音書 フランクの高弟で作曲家のヴァンサン・ダンディが、敬愛する師のために筆をとった思い出の書。 伝記としてだけではなく、優れた芸術論・教育論としても読める名著。 昭和28年刊行の音楽之友社版を復刊。 ★フランク生誕200年記念 著者は単に外側から第三者としてフランクを眺めたのでなく、かえってフランクの 魂の内奥に触れ、真の音楽精神が何であるかを、いわば秘伝的にフランクから直々に学んだ。したがって著者はフランクの本領を的確に把握し、権威をもって「これがフランクだ」と言い切ることができたのである。――「訳者あとがき」より 《目次》 第1 部 人間としての先生 1 先生の生涯 2 先生の人となり 第2部 先生の作品 1 先生の作品の系譜 2 先生の愛好された音楽 3 先生の作曲法 4 第1期(1841~1858) 5 第2期(1858~1872) 6 第3期(1872~1890) 7 「弦楽四重奏曲ニ長調」 8 「三つのオルガンコラール」 9 「至福」 第3部 教師としての先生 1 フランク「お父さん」 2 フランク楽派 作品年表 訳者あとがき 《著者略歴》 ヴァンサン・ダンディ 1851年生まれ。1931年没。フランスの作曲家。1872年にパリ音楽院に入学し、セザール・フランクの弟子となる。1894年にはシャルル・ボルドやアレクサンドル・ギルマンとともに音楽学校のスコラ・カントルムを設立。指揮者や教育者としても広く活動し、フランス近代音楽の推進者として活躍した。作曲での代表作品は「フランスの山人の歌による交響曲(セヴェンヌ交響曲)」、交響的変奏曲「イスタール」など。 著作は本書のほかに『ベートーヴェン(Beethoven; Biographie Critique)』(小松耕輔訳、音楽之友社)、『作曲法講義(Cours de Composition Musicale)』(池内友次郎訳、古賀書店)などがある。 《訳者略歴》 佐藤 浩(サトウ ヒロシ) 1915 年生まれ。2002 年没。翻訳書にパウル・ヒンデミット 著『作曲家の世界』、イーゴリ・ストラヴィンスキー 著『音楽とは何か』、J. クロード・ピゲ 著『音楽の発見』、(すべて音楽之友社刊)などがある。
-

新版 名曲この一枚
¥2,750
クラシックファンの間で伝説となっている異色のLPガイド『名曲この一枚』(1964年、文藝春秋新社刊)を新版で満を持して刊行! 戦前から1980年代まで「DISQUES」、「芸術新潮」、「ラジオ技術」でレコード評を執筆。レコードに対する感動をあけっぴろげな名文で綴り、多くのファンを魅了してきた「盤鬼」こと西条卓夫の名著『名曲この一枚』を新版として刊行! ティボー、ランドフスカ、エネスコ、カペー……今なお色褪せない名演の数々の魅力を情熱的に語り尽くす。 今回新たに「藝術新潮」に掲載された随筆11本を収録。現在の読者に向けて対応CD一覧も付けた。 《目次》 1 名曲この一枚 まえがき Ⅰ ヴィタリからへンデル Ⅱ ハイドンからべートーヴェン Ⅲ シューベルトからブラームス Ⅳ フランクからオネゲール 2 盤鬼随筆集 ティボーとの七日間 ティボーを悲しむ 三十三のプロフィール 盤鬼随想―音ありき― 反時代的レコード談義 レナーとプランテ 王者クライスラー エレキ前夜 盤鬼秘蔵の九箱 ランドフスカとともに 犬印へのあこがれ 遊廓で開いた視聴会 最後のレコード・ファン―野村胡堂の死― 好楽家の皆様へ―父に代わって― 西条良彦 名曲この一枚 対応CD一覧 掲載曲名索引・演奏者名索引 《著者略歴》 西条 卓夫(さいじょう たくお) 明治37年三重県生まれ。慶応義塾大学予科在学中に作家で音楽評論家の野村胡堂氏と出会い、クラシック音楽に目覚める。以来、戦前は「DISQUES」誌、戦後は「藝術新潮」(1954~1978)や「ラジオ技術」(1955~1986)で長きに亘りレコード評を担当したレコード音楽鑑賞界の大先達である。自ら「盤鬼」と号している。体当たりで聴いて体当たりで書く名調子の文章により、幾多のレコードファンを生み惹きつけてきた。また数々の復刻LPを企画、ティボーやランドフスカの魅力を江湖に広めた。著書に『レコード音楽夜話』(久禮傳三名義、内田老鶴圃刊)、訳書にジャック・ティボー『ヴァイオリンは語る』(石川登志夫共訳、新潮社刊その後フランス音楽文化愛好会復刊)がある。
-

今だから! 植木等 “東宝クレージー映画”と“クレージー・ソング”の黄金時代
¥3,520
今だからこそ見たい! 聴きたい! 植木等の映画と歌 映画、歌、発言、人間から多面的に解き明かす〈植木等の真実〉 貴重な東宝カラー・スチール、ご家族提供による秘蔵写真 多数掲載。 植木等研究本の決定版! 【本書の内容】 ①クレージー世代の筆者が“東宝クレージー映画”の代表作と“クレージー・ソング”を語り尽くす! ②『ニッポン無責任時代』の主人公・平均(たいらひとし)にはモデルがいた! その意外な人物とは? ③初めて聞く!『 クレージー黄金作戦』ラスベガス・ロケに参加したスタッフによる現地レポート ④植木等が残した言葉から、〈無責任男の呪縛〉を吹っ切った時期を読み解く。 ⑤“最初の付き人兼運転手”小松政夫さんに聞く、植木等と過ごした三年十か月。「 やっぱり植木等は、特別です……」(小松政夫) ⑥“最後の付き人”藤元康史氏が語る晩年の植木等。〈 植木等に国民栄誉賞が与えられなかった、その本当の理由〉とは? ⑦植木等が出演した8ミリ自主映画と教育映画があった!――幻の作品『刑事あいうえ音頭』と『おんぷ』を徹底紹介 ⑧バック・ミュージシャンを務めた斎藤誠が、音楽家としての植木等を語る! 《著者略歴》 高田 雅彦(タカダ マサヒコ) 『七人の侍』と『ゴジラ』公開の翌年、1955 年1月、山形市生まれ。実家が東宝の封切館「山形宝塚劇場」の株主だったことから、幼少時より東宝映画に親しむ。黒澤映画、クレージー映画には特に熱中。以来、成城学園に勤務しながら、東宝映画研究をライフワークとする。現在は、成城近辺の「ロケ地巡りツアー」講師と映画講座、映画文筆を中心に活動。 著書に、『成城映画散歩――あの名画も、この傑作も、みな東宝映画誕生の地・成城で撮られた』、『三船敏郎、この10 本――黒澤映画だけではない、世界のミフネ』(以上、白桃書房)、『七人の侍 ロケ地の謎を探る』(アルファベータブックス)、共著に『山の手「成城」の社会史』(青弓社)がある。
-

あと四十日 “フルトヴェングラーの証人”による現代への警告
¥2,200
ベルリン・フィルの首席ティンパニー奏者をかつて務め、話題となった『フルトヴェングラーかカラヤンか』の著者でもあるヴェルナー・テーリヒェンが最後に遺したメッセージ。 魂が滅びるとき、世界も滅びる。 フルトヴェングラーの元でティンパニー奏者を務め、彼の中から「女性的性質」を感じ取ったテーリヒェン。感受性を豊かにし、受け入れ、共感する——。利己主義、権威主義、拝金主義から芸術ひいては人間を救うため、テーリヒェンが最晩年に遺したメッセージ。 テーリヒェンの晩年の論説、講演録、そして聖書のヨナ書を題材にした最後の作曲作品・音楽劇《あと四十日》の脚本を収録。 テーリヒェン生誕100年記念出版。 《目次》 はじめに 第1章 内面を見つめて(1995年にミュルツツーシュラークでの指揮者講習会の講習生のために刊行された小冊子より) フルトヴェングラーを手掛かりに/男性的な作曲と女性的な作曲 第2章 講演 フルトヴェングラーに見る、演奏の魅力と誠実 ( 第一回ドイツイエナ大学で開催されたフルトヴェングラー・ターゲでの講演) 第3章 魂の言葉 ヴィルヘルム・フルトヴェングラー没後50周年によせて 第4章 音楽劇《あと四十日》 おわりに テーリヒェンが遺したメッセージと現代 ヴェールナー・テーリヒェン年譜 《著者・編訳者略歴》 ヴェルナー・テーリヒェン(Werner Thärichen) ティンパニ奏者・作曲家。1921年ノイハルデンベルク生まれ。48年から 84年までベルリン・フィルハーモニー管弦楽団に在籍。フルトヴェングラーとカラヤンのもとで首席ティンパニー奏者を務めた。作曲作品はチェリビダッケ、ヨッフム、カラヤンらが指揮している。著作に『Paukenschläge』(邦訳『フルトヴェングラーかカラヤンか』1998年 高辻知義訳 音楽之友社のち中公文庫)、『Immer wieder Babylon oder Musik als Sprache der Seele』( 邦訳『あるベルリン・フィル楽員の警告 心の言葉としての音楽』1996年 平井吉夫・高辻知義訳 音楽之友社)がある。2008年に86歳で没。 野口 剛夫(ノグチ タケオ) 作曲家・指揮者・音楽学者。1964年東京生まれ。中央大学大学院(哲学)、桐朋学園大学研究科(音楽学)を修了。現在東京フルトヴェングラー研究会代表。著書に『フルトヴェングラーの遺言』(春秋社)、訳書にシェンカー『ベートーヴェン第5交響曲の分析』(音楽之友社)、フィッシャー=ディースカウ『フルトヴェングラーと私』(河出書房新社)、『伝説の指揮者フェレンツ・フリッチャイ』(アルファベータブックス)他がある。2014年『新潮45』掲載の論説、「“全聾の天才作曲家”佐村河内守は本物か」により第20回「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」作品賞を受賞。
-

名曲200でわかるロックの歴史と精神 ALL TIME GREATS ROCK AGE
¥2,970
英米のポピュラー音楽200曲を通して、リアルタイムの体験に基づき綴られる“ロックの時代”。 1955~85年、それはまさに「ロックの時代」であった。本書では、その30年間におけるアメリカ、イギリスのポピュラー音楽から各100曲、計200曲をセレクトしランク付け。有名どころのみならず、幅広いアーティストを取り上げ楽曲単位で批評する。黄金期のロック・シーンにリアルタイムで触れてきた著者自身の体験もまじえ、当時の熱気を描き出す。 単なる楽曲解説やノスタルジーに終始しない、音楽を愛する全ての人へ送る一冊! その他にも、「ロックンロール以前のポップス」、「日本における洋楽ロック」、「Jポップ・ロックのルーツ」各章にて、重要曲をセレクトし短評を付す。 《目次》 Ⅰ: Intro(序章) Ⅱ: Pre - Rock ’N’ Roll Years(ロックンロール以前のポップス) Ⅲ: U.S. Rock-TOP100 1955-1985 Ⅳ: U.K. Rock-TOP100 1955-1985 Ⅴ: Yogaku In Japan(日本独自の洋楽ヒット) Ⅵ: Roots of J-POP/ROCK TOP 40(Jポップ/ロックのルーツ) 《著者略歴》 三宅 はるお(ミヤケ ハルオ) 音楽ライター。1949年東京生まれ。明治学院大学文学部英文科卒業。出版社退社ののち、FM東京の深夜番組の訳詞コーナーを担当。ロック喫茶「レインボー」のDJを経て、75年から『音楽専科』に寄稿。以降『GUTS』『レコード・コレクターズ』などのレギュラーに加え、伊藤政則らと共に雑誌『ROCKADOM』を発刊。ラジオDJ/構成、フリー・ペイパー『WHAT’S NEW』編集、青山レコーディング・スクール講師など、幅広い活動を続ける。さらにロック・クラシック系のライナーノーツなどで、評論活動を続けている。また、キンクスのレイ・デイヴィス、ニール・ヤング、レナード・スキナードなどへの豊富なインタビュー経験もあり。著書に『ストーンズが大好き』(サンドケー出版局)、『ロックとポップスの歴史』(ヤマハミュージックメディア)、『レッド・ツェッペリン』(音楽専科社)など、訳書に『ザ・ビートルズ 1962-1970 ザ・コンプリート・ストーリー』(音楽専科社)、『クイーン 伝説のチャンピオン』(音楽専科社)などがある。
-

ベートーヴェンは怒っている! 闘う音楽家の言葉
¥1,980
現代人よ、いま彼の言葉から学べ! 大衆に迎合しない。現状に妥協しない。高い理想をかかげ、そのギャップと闘いながら誰よりも人間らしく生きようとしたベートーヴェン―混迷を極めるいま、彼が遺した言葉の数々に改めてスポットライトを当てる。 【生誕250 年記念出版】 ベートーヴェンの言葉を、手紙、日記、手記、メモ、他人の述懐などから選び出し、それを年代順に掲載。それぞれに解説を付す。新型コロナ・ウイルスが明るみにしたものを音楽家の視点から綴った、野口剛夫「ベートーヴェンは怒っている」も収録。 《目次》 はじめに 1777~1801 1802~1811 ベッティーナ・ブレンターノの回想によるベートーヴェンの言葉 1812~1818 ベートーヴェンとゲーテの違い 1819~1827 ベートーヴェンは怒っている野口剛夫 あとがき 《編著者紹介》 野口 剛夫(ノグチ タケオ) 1964 年東京生まれ。中央大学大学院(哲学)、桐朋学園大学研究科(音楽学)を修了。現在東京フルトヴェングラー研究会代表。著書に『フルトヴェングラーの遺言』(春秋社)、訳書にシェンカー『ベートーヴェン第5交響曲の分析』(音楽之友社)、フィッシャー=ディースカウ『フルトヴェングラーと私』(河出書房新社)、『伝説の指揮者フェレンツ・フリッチャイ』(アルファベータブックス)他がある。2014 年『新潮45』掲載の論説、「“全聾の天才作曲家”佐村河内守は本物か」により第20 回「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」を受賞。
-

函館 歌と文学の生まれる街 その系譜と精神風土
¥2,750
函館慕情…不思議な魅力を秘めた精神風土から生まれた人と作品―「函館の女」北島三郎、GLAY、小説の魔術師久生十蘭、亀井勝一郎、映像で甦る佐藤泰志、辻仁成、警察小説の今野敏…函館は、歌謡曲に多く歌われ、そして多くの多彩な作家を輩出した街である。本書ではその代表的な歌謡曲や文学の魅力をあますところなく紹介する。 「函館をはじめ北国を歌った歌謡曲はたくさんあるが、のちに北原ミレイが歌った『石狩挽歌』は、とりわけ船頭として行った鰊漁場で船が転覆して不慮の死をとげた父の記憶と強く結びつき、こころ揺さぶられるものがあった。」(「まえがき」より) 《目次》 第1章 函館慕情 ― 『津軽海峡・冬景色』『石狩挽歌』『函館の女』 第2章 川内康範、GLAY、『函館ハーバーセンチメント』、『北の旅人』 第3章 函館と森町 ― 石川啄木と李恢成『加耶子のために』 第4章 海外放浪文学の先駆者 ― 長谷川海太郎(谷譲次・牧逸馬・林不忘)の軌跡 第5章 「小説の魔術師」と『新青年』の編集長 ― 久生十蘭と水谷準 第6章 望郷の文学者 ― 亀井勝一郎と「函館八景」 第7章 シベリアと満州を生きる ― 長谷川四郎の生き方 第8章 格差社会の暗部を照らす ― 映像で甦る作家・佐藤泰志 第9章 トポスとしての函館 ― 辻仁成の作品 第10章 エンターテイメント系の作家 ― 谷村志穂、宇江佐真理、今野敏 《著者略歴》 吉岡 栄一(ヨシオカ エイイチ) 1950年、北海道生まれ。法政大学大学院英文学専攻博士課程満期退学。トルーマン州立大学大学院留学。東京情報大学名誉教授。日本コンラッド協会顧問。日本オーウェル協会元会員。『マーク・トウェイン コレクション全20巻』(彩流社)を責任編集。著書に『ジョージ・オーウェルと現代』、『村上春樹とイギリス―ハルキ、オーウェル、コンラッド』、『青野聰論―海外放浪と帰還者の文学』、『文芸時評―現状と本当は恐いその歴史』(以上、彩流社)、『亡命者ジョウゼフ・コンラッドの世界』(南雲堂フェニックス)、『単独者のつぶやき 書評と紀行』(鼎書房)、共著に『文学の万華鏡―英米文学とその周辺』(れんが書房新社)、『英米文学にみる仮想と現実』(彩流社)、『亡霊のイギリス文学 豊饒なる空間』(国文社)、『オーウェル―20世紀を超えて』(音羽書房鶴見書店)、『イギリス文化事典』(丸善出版)、『英語の探検』(南雲堂フェニックス)、共訳に『オーウェル入門』、『気の向くままに 同時代批評1943-1947』(以上、彩流社)、『思い出のオーウェル』(晶文社)、『開高健の文学世界』(アルファベータブックス)など。
-

昭和軍歌・軍国歌謡の歴史 歌と戦争の記憶
¥5,940
昭和の時代を中心とする近代日本の軍歌と軍国歌謡の歴史を、日清、日露戦争から満洲事変、日中武力紛争、そして大東亜戦争の開始から敗戦まで、戦史とともに考察する!! 軍歌・軍国歌謡の約3000 曲にのぼるディスコグラフィーを付す!! 《目次》 Ⅰ 軍歌から軍国歌謡へ…1 明治国家と軍歌/2 満洲事変と軍歌/3 国内情勢と国際的孤立 Ⅱ 昭和軍国歌謡の時代…1 日中武力紛争の拡大と軍国歌謡/2 新体制運動と軍国歌謡 Ⅲ 歌でつづる大東亜戦争史…1 大東亜戦争の戦端を開く/2 大東亜共栄圏の夢/3 激化する日米の攻防戦/4 決死の戦いと敗北/5 徹底抗戦と敗戦への途 《著者略歴》 菊池 清麿(キクチ キヨマロ) 音楽評論・歴史家。一九六〇年生まれ、明治大学政経学部卒、同大学院修了。日本政治思想史を橋川文三、柳田国男の思想を後藤総一郎に師事する。近代と反近代の諸問題をテーマに藤山一郎、中山晋平、古賀政男、服部良一、古関裕而など近代日本音楽家評伝を中心に著作活動し著書多数。主な著書に、『中山晋平伝』(郷土出版社 2007)、『日本流行歌変遷』(論創社 2008.4)、『永遠の歌姫佐藤千夜子』(東北出版企画 2008)。『私の青空 二村定一』(論創社 2012)、『評伝 古関裕而』(彩流社 2012)、『評伝 服部良一』(彩流社2013)、『天才野球人 田部武雄』(彩流社2013)『評伝 古賀政男』(彩流社2015)、『ツルレコード 昭和流行歌物語』(人間社2015)、『昭和演歌の歴史』(アルファベータブックス)他多数。
-

ホロヴィッツ 全録音をCDで聴く
¥3,850
ホロヴィッツの生涯にわたってなされた録音(1928~1989)を一貫して論じるとともに、全てをCDで聴けるようにガイドする。 86年の生涯のなかで4度にわたる引退、復帰を繰り返しながらも、死の4日前までレコーディングに挑み、最後まで《現役のピアニスト》としてピアノに殉じた巨匠ウラディミール・ホロヴィッツ (1903~1989)。その人生は当時の社会情勢や政治、経済に翻弄されながらも常に録音と共にあった。録音というモニュメント=メディアを通じて、この人間臭いピアニストの遺産を振り返る。 【全録音ディスコグラフィー付】没後30年記念出版。 《著者略歴》 藤田 恵司(フジタ ケイジ) 1978年1月22日、20世紀を代表するピアニスト、ウラディミール・ホロヴィッツ(1903 ~1989)のアメリカ・デビュー50周年記念演奏会の2週間後に生まれる。中1のときにたまたま音楽の授業で聴いた往年の名ヴァイオリニスト、ミッシャ・エルマン(1891~1967)の弾く「ツィゴイネルワイゼン」[VANGUARD]がきっかけでクラシック音楽の魅力に目覚める。後に旭川出身の音楽評論家、故・佐藤泰一氏(1938~2009)との親交やコンサートで旭川をたびたび訪れたウィーンのピアノの巨匠、故・イェルク・デームス(1928~2019)に接し、ピアノ曲やピアニストにおける世界の奥深さを知る。2007年9月から2009年8月まで旭川市・大雪クリスタルホールの運営協議委員を務める。「クラシックジャーナル047 クラシックCD 最終形態としてのBOX」(アルファベータ2013年)中の「50のBOXに聴くピアニストの至芸」を執筆。
-

冼星海とその時代 中国で最初の交響曲作曲家
¥3,850
中国では国歌「義勇軍進行曲」の作曲者・聶耳と並ぶ国家的英雄である冼星海(一九〇五〜一九四五)。辛亥革命から日中戦争終結まで、混乱の時代を太く短く生きた。パリ音楽院でポール・デュカより作曲を学ぶが、帰国後は戦意高揚を目的とする大衆音楽の作曲と歌唱指導に尽力する。しかし、胸の内には「交響曲を作り、中国のベートーヴェンになる!」という強い思いを持ち、密かに創作を進めていた…。 政治のための芸術と個人の芸術との間で葛藤するひとりの作曲家の生涯を、激動の中国近現代史とともに鮮やかに描く! 《目次》 ●序章 中国近現代史への誘い/抗戦名曲「黄河大合唱」 ●第一章 生まれてから留学まで 生涯の概要/生年月日について/誕生からシンガポール時代まで/広州嶺南大学での学習/北京での学習/上海での学習と「普遍的音楽」 ●第二章 パリ留学 留学のいきさつ/冼星海による記述/スコラ・カントルムでの学習/パリ音楽院での学習/プロコフィエフとの関係 ●第三章 救亡音楽運動家・冼星海の誕生 帰国とその後の西洋音楽との関わり/左翼音楽運動とは何か/左翼音楽運動との関わり ●第四章 武漢から延安へ……『大合唱』の創出 延安への道/一九三〇年代末の音楽情勢/武漢までの楽曲/歌劇「軍民進行曲」/「生産大合唱」 ●第五章「黄河大合唱」と入党 「黄河大合唱」の成立/入党について ●第六章 ソ連での彷徨と死 延安からモスクワへ(訪ソの目的)/モスクワにて(続・訪ソの目的)/冼星海の最後の手紙/モンゴルとカザフスタン/モスクワでの死/第一交響曲をめぐって ●終章 芸術性と大衆性の間で/魯迅芸術学院の正規化・専門化から文芸座談会へ 後記/冼星海略年譜/冼星海楽曲年譜 《著者略歴》 平居 高志(ヒライ タカシ) 1962年、大阪府生まれ。1988年、東北大学大学院文学研究科博士課程前期修了(中国学)。1989年より、宮城県県立高校教諭(国語科)。女川、石巻、仙台第一、水産の各校を経て、現在は塩釡高校に勤務。2017年、東北大学・博士(文学)。著書:『「高村光太郎」という生き方』(2007年、三一書房)、『それゆけ、水産高校!』(2012年、成山堂書店)。論文・雑文:中国近現代史、水産海運業後継者育成、東日本大震災関連など多数。ブログ:「Tr, 平居の月曜プリント」(https://takashukumuhak.hatenablog.com/)
-

静寂の中に、音楽があふれる ピアニストが語る!《現代の世界的ピアニストたちとの対話 第四巻》
¥3,520
SOLD OUT
大好評の人気シリーズ第4弾! 世界的ピアニストたちが長時間インタビューに応じ、芸術、文化、政治、社会、家庭、人生について語る! 巻頭ロング・インタビューは日本でも人気の高いピアニスト、アンドラーシュ・シフ(11 月に自身の古楽器アンサンブルと共に来日予定)!! また、生前最後のゾルタン・コチシュのインタビューも収録。日本人ピアニスト、小山実稚恵と横山幸雄も登場!! <本書に登場するピアニスト> アンドラーシュ・シフ/ゾルタン・コチシュ/デジュー・ラーンキ/スティーヴン・ハフ/シプリアン・カツァリス/コンスタンチン・リフシッツ/アレクセイ・リュビモフ/アレクサンドル・メルニコフ/コンスタンチン・シチェルバコフ/ユリアンナ・アヴデーエワ/ボリス・ベレゾフスキー/ヴァレリー・アファナシエフ/小山実稚恵/横山幸雄 《著者・翻訳者略歴》 焦 元溥(チャオ・ユアンプー) 1978年、台北生まれ。国立台湾大学卒。 大英図書館特別研究員としてキングス・カレッジで音楽専攻。音楽研究家。著書に『作曲家の意図は、すべて楽譜に! 』『音符ではなく、音楽を! 』(いずれもアルファベータブックス)